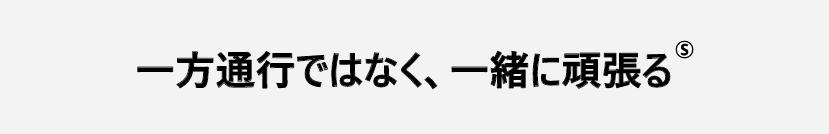出会い、自信、強い意志。運動が苦手な子どもがオリンピック選手になるまで
オリンピック選手が「運動が苦手な子どもだった」と語っても、多くの人はすぐに信じることができないだろう。己の肉体一つで限界に挑戦する陸上競技において、三段跳で実に12年ぶりのオリンピック日本代表に選ばれた長谷川大悟は、体も小さく理科が好きな内向的な少年だった。「流されるようにして始め、何度も辞めようと思った」という陸上競技において、長谷川は節目節目で出会いに恵まれながら、才能を開花させていく。自身の経験から「可能性を感じられる機会が大事」「挑戦できる社会をつくりたい」と言う長谷川に、五輪を経験した現役選手として、また社会貢献をするアスリートとして、今目指しているものを聞いた。
Interview / Chikayuki Endo
Text / Atsushi Kuramoto
Photo / Naoto Shimada and Saya Araki
Interview date / 2023.07.14
弱い自分の支えになった「人間本気になれば大差なし」という言葉

――幼少期は運動が苦手だったとうかがいました。五輪に出るほどの選手が幼少期に運動嫌いだったというのはとても意外です。
「嫌い」というよりは「できなかった」んですよね。小学校の頃は運動というと主に体育の授業になると思いますが、僕は体が小さくて力も弱く、何をするにも人並み以下だったので全然楽しめませんでした。クラブ活動はパソコン部や理科実験部に所属していました。ゲームが好きな、どちらかというと内向的な少年だったと思います。
――もともとパソコンや理科は好きだったのでしょうか。
外に遊びに行くよりも塾に行って勉強するほうが好きでした。両親も子どもに運動をやらせようという感じは特にありませんでした。あとはゲームが大好きでしたね。小学生の頃にポケモンが発売されてからは、ポケモンばかりやっていた記憶があります。任天堂に入ることを夢見る少年でした。
――運動嫌いだった長谷川さんが中学生から陸上を始められたのは何か理由があったのでしょうか。
友人に誘われて陸上部に入部したのがきっかけです。僕の入った中学は公立だったので小学校から仲の良い友達もそのまま一緒に進学したのですが、その友人が運動部に興味があって。ふたりで一緒にいろんな部を見て回るうちに、彼が「陸上をやってみたい」と言い出したので、僕もなかば流されるような形で入部しました。
――陸上競技を始めてみた感想はいかがでしたか?
第一感としては「自分には向いていないんだろうな」でしたね(笑)。実際、中学1年生の頃は身長も140センチ台で背の順に並ぶと前から2番目でした。体ひとつでやらなければならない陸上競技において、フィジカル面では圧倒的に劣っていたんです。砲丸投げや棒高跳などさまざまな競技に挑戦しましたが本当に何にもできなくて、かろうじてできたのが走幅跳。だからこの競技を選んだのも、最初は消極的な選択だったように思います。しかもその走幅跳も、中学時代は女子部員に勝てないくらいのレベルでしたからね。

――向いていないと自覚しつつも続けられた理由は、どこにあったのでしょうか。
誘ってくれた友達と、顧問の先生の存在が大きかったと思います。僕自身が運動に苦手意識を持っていたこと、体が小さく体力が無かったこともあって、練習メニューを全部こなせない日も多かったんです。そういう選手に対して「ちゃんとやれ!」と叱ったり、あるいは見切ったりする指導者もいると思うのですが、顧問の先生は「長谷川は長谷川の目標に沿ってやっていけばいい」と向き合ってくれました。「今日はこれができた」と、ひとつひとつの成長を自分の中での自信にできるようになってからは、陸上部での日々を前向きに捉えられるようになりました。塾がある日は部活を早く切り上げて帰ることも許されていましたし、良い意味で適当にやることができた環境が、続けられた大きな理由だったのかもしれません。
――その先生との出会いがなければ、五輪選手・長谷川大悟は生まれていなかったかもしれないと。
間違いなくそうですね。今でも覚えているのですが、その先生は常々「人間本気になれば大差なし」と仰っていました。今どんなレベルであれ、本気で取り組めばそんなに大きな差は生まれないんだよと。その時はなんとなく聞き流していましたが、いまだにこうしてすぐ思い出せるほど、後々の自分にとって大きな支えになった言葉です。もともと1番になりたいというような気持ちは一切ありませんでした。だけど、先生の指導と言葉のおかげで、弱い自分に劣等感を抱くこともありませんでした。
――中学時代の記録は、どのくらいだったのですか?
一度だけ5メートルを超えられた試合があって、あとは4メートル台でした。中学時代に賞状を1枚だけ貰ったことがあって、それは4メートル5センチの記録で区大会3位に入賞したときのものです。実は参加者が4人しかいない小さな記録会だったんですけどね(笑)。当時は大きな記録も出せていなかったので、陸上で記録を残したいというよりも、いずれは進学校に進んで良い大学に入りたいというような漠然とした思いを持っていました。高校でも陸上を続けるつもりはありませんでしたね。
人生を変えた「取り組み方」を教えるコーチとの出会い

――そんな長谷川さんが、桐蔭高校に一般入試で入学した後も陸上を続けたのはなぜですか。
進学した桐蔭学園の陸上グラウンドがタータントラック(※現在の陸上競技場のスタンダードになっている合成ゴム)だったことが大きかったです。それまで経験していなかった環境が良いグラウンドで陸上をやってみたいと思いました。とはいえ、自分から積極的に見に行くモチベーションは無く、中学の時と同様に、クラスで仲良くなった友達に誘われて流されるように見学にいき、そのまま入部しました。
――高校の陸上部では、周りのレベルはどうでしたか。
レベルはすごく高かったですね。推薦入学ですごい記録を持つような選手も数多く入部していました。ただ僕自身はインターハイの存在も知らないぐらい記録を出すことや競うことに興味が無かったので、周りのこともあまり気にしていませんでした。実際に競技を始めても、「高校の練習はさすがにきついな」と感じていたくらいです。ただ、そんな意識だったにも関わらず、1年生の秋には5メートル70センチを跳べるようになったんです。ちょうどこの頃に身長が急激に伸びたことも大きかったと思うのですが、夏場のハードな練習を乗り越えていたこともあって、「練習すれば記録が伸びるんだ」という実感を得ることができました。
――三段跳を始められたのも高校時代だそうですね。
高校2年生の秋の新人戦が三段跳のデビューでした。2年になってすぐ、部に外部のコーチを招いたのですが、その方が棒高跳の選手だったんです。跳躍に詳しいその方に、「三段跳もやってみたら」というある種軽く誘われたのがきっかけでした。
――三段跳という競技をいざやってみて、いかがでしたか。
不思議でしたね。シンプルによくわからない種目だと思いました。走幅跳のような気持ちよさがなく、考えながらやらないといけない。だから難しい競技という印象を受けました。「右・右・左で跳ばなければいけないのはどうしてなのですか?」という感じ(笑)。ですので、自分がこの種目にあっているとも、記録が残せるとも思っていませんでした。
――そういったスタンスの長谷川さんと、推薦で入ってくるような、とにかく勝つことを目的としている他の部員との間に温度差ができるようなことはありませんでしたか?
実はその頃、部に大きな変革があって。高校2年生の時にAチームとBチームに分かれて動くようになったんです。Aチームが推薦入学で第一線で記録を作る組、Bチームは高校になって陸上をはじめたり、記録が残せない人たちのチーム。そのためそれぞれが別々の意識で陸上に取り組むようになりました。私はBチームにいたのですが、Bチームの中ではそれぞれの目標達成が尊重されていたので、個々人で勝つこと、記録を出すことを目的としたAチームよりも結束していたように思います。

――しかし、記録を目指さないチームにいながら、長谷川さんは最終的にはインターハイに出場されていますよね。
先程話した、外部からきたコーチがBチームを指導することになったのですが、そのコーチの指導を受けたことをきっかけに、陸上に本気で取り組むことになったんです。そのコーチは記録ではなく、競技を通じた人間力の成長に価値を置く方でした。また、今思えばすごく選手のやる気を引き出すのがうまい方でもあったんです。たとえば砂場の整備もいちばん最初にコーチが来てやるんですよ。そんな姿を見ていると、生徒も「あ、コーチがやるんじゃなくて自分たちがやらないとだめだよね」と思わされる。そういった形で、さまざまな学びや気付きをくれるコーチで、「コーチがこういう風にやっているから自分たちも頑張らないといけない」と感じさせてもらえる場面が多くありました。競技に取り組む姿勢を学ばせてもらったと思います。記録で怒られたことは一切ありませんでしたが、態度で怒られることはありましたね。競技に対する気持ちも鍛えられました。Bチームはもともと期待されていた選手たちではないにせよ、全力でバックアップしてくれるコーチのおかげで団結力がありました。そのため、最終的にはAチームに匹敵する記録を出す選手も生まれ、私自身もインターハイに出られるレベルになりました。全体的に選手が育ったということだと思います。
――選手として伸びていくためには身体能力や技術はもちろんですが、日々の取り組む姿勢やマインドも大事、ということでしょうか。
むしろそれだけだった気がします。フィジカルで勝てない部分をどうやって埋めていくかを考えた時に、練習量や練習に向き合う姿勢、どれだけ準備ができてどれだけ気持ちを練習に向けられるかや、勝ちへの貪欲さ、そういったひとりひとりの強みをバックアップしてくれていました。その結果、僕たちも弱いながらも自分自身ができることを一生懸命やろうという気持ちを作ることができ、自己肯定感をもって競技に取り組めるようになりました。
――素晴らしいコーチですね。お名前をうかがってもいいですか。
八木祐介先生です。いまでも僕のコーチをしていただいています。高校2年生の時からなのでもう15、6年お世話になっています。
――ただ、高3で出場したインターハイでは「記録なし」に終わったそうですね。
悔しい気持ちも当然ありましたが、それ以上にこれまでやってきた結果としてインターハイに出られたということに満足していました。Bチームのみんなからもハチマキにメッセージを書いてもらったり、すごく応援してくれたことを覚えています。インターハイに出たことで、三段跳を僕よりももっと前からやっていた選手たちとは経験だけでなく意識の持ち方が違っていると感じられたことが、大学でさらに上を目指していこうと考えるきっかけになりました。
自身の強みの「考える力」で五輪出場を果たす

――東海大学に進学されてから陸上部に入るまで、少し時間が空いていますね。これはどうして?
入部したのは6月なので、入学から2か月も入部を迷っていたことになりますね。インターハイで出会った選手たちと仲間になって彼らの試合を応援しにいくうちに、また試合に出てみたいという気持ちが湧いてきたのですが、その一方で東海大学のレベルの高さに圧倒されて、入部を渋っていたんです。また、情報理工学部に進んでいて単位数も多い中、授業後に練習をやるということにも不安がありました。でも最終的にはすでに入っていた陸上部員に勧誘され続けて、入部を決断しました。
――節目節目で陸上に誘ってくれる友達がいたのですね。
陸上を始めたのも続けたのも友人の影響ですね。僕は自分で踏み切れる性格じゃなかったので、直感的に動くことができなくて。毎回何かに取り組もうとするたびいろいろと考えてしまうので、後押ししてくれた友人達には感謝しかありません。
――高校時代までは記録にこだわらないスタンスでしたが、大学に入ってからは意識の変化はありましたか。
自分のなかで「続ける以上は後悔をしないようにしたい」と決めていたので、それならばどうすれば自分が満足できるかを考えました。そして、自身に対して「日本一になる」という目標を掲げました。それまでの陸上人生では一線を引いて、記録にこだわるようにしたんです。さらに、どうせやるならとことん後悔がない形でやりたいと思い、八木コーチに引き続き指導いただけるようにお願いしました。大学にもコーチはいたのですが、僕の場合は高校の恩師である八木さんに見てもらうことがほとんどでした。ただ、大学陸上部での活動が順調だったかと言われると、難しい部分も多々ありましたね。そもそも自分よりも跳べる選手がたくさんいるので、最初は無力感のほうが強かったです。ケガもしましたし、練習時間も限られていて、大変ではありました。
――そんな苦境の中で結果を出せた秘訣は、どこにあったのでしょうか。
とにかく効率を大切にしました。そのひとつに、思い切って大学で練習しないという選択もありましたね。学校のグラウンドは使える時間が限られていたこともあり、授業で遅くなってしまうと、練習時間が短くなってしまうんです。そのため、授業後すぐに自宅近くの競技場に移動し、がっつり練習するというメニューに切り替えました。
――大学の部活はそういった選択肢も選べるほど、自由だったんですね。
いえ、今思えば結構強引な選択でしたし、特別に近い扱いに対して快く思っていなかった人もいたと思います。ですが、授業があるという大前提の中で成果を出すにはこうするしかないと思い、顧問の先生に相談して理解していただきました。

――長谷川さんの発想や行動は、すごく論理的に考えられていますね。
自分に自信がないので(苦笑)、いろんな情報を得て、組み立てながら物事を考えるようになったんだと思います。
――論理的に考える力は競技にも生かされていますか。
自分でいうのはおこがましいのですが、それが僕の強みだと思います。練習ひとつひとつの感覚だったり取り組みだったり物の使い方だったりをすごく考えるので、そこで効率を高められたとも思います。ウエイトトレーニングにしても、バーを持つ位置、タイミング、スピード、意識する部位など、とても細かく考えながら行っています。
――その強みに気づいたのはいつですか。
大学に入ってからです。大学に入って同じ競技をやっている人を多く目にする中で、自分はこだわりを持った練習をしているんだと気付くことができました。
――インカレで優勝されたことが、五輪を目指すきっかけになったのでしょうか。
最初のきっかけは、大学2年時のインカレで準優勝できたことでした。その時に「もし将来陸上を続けるとすれば大学のうちに日本代表になれないと見込みがない」と思ったので、代表を目指すことにしました。ですが、大学3年になって就職活動を始めた時点では、将来陸上を続けるかはまだ決めかねていて。陸上部がある企業、無い企業どちらもこだわりなく受けて、もし陸上を続けられそうな企業に採用されたらそのまま続けるかもしれない、というどっちつかずな気持ちでいました。陸上で五輪に行くのは簡単なことではありませんし、社会人になっても続けることは、言葉を選ばずに言うと割に合わない場合も多いですから。だから、ようやく社会人になっても陸上を続けてもいいのかもしれないと考えられるようになったのは、実際に大学3年でインカレで優勝できて、大学4年の時にアジア選手権の日本代表になれた時です。子どもの頃から陸上選手に憧れがあったわけではなかったけれど、目の前の目標にひたすら向きあってきた結果、オリンピックを目指せるところまで来たという感覚でした。
――大学卒業後は日立に入社し、実業団選手として活動されています。実業団での生活はどのようなものでしたか?
9時始業で16時、17時まで勤務。そこから一度帰宅し競技用の荷物をもって17時半か18時から練習開始。毎日3時間から4時間練習をして帰る生活です。1年目から東日本の新人賞を取ったりと滑り出しとしては悪くなかったのですが、両立は大変でした。セルフケアに目を向け、食事と睡眠の質をあげるように意識しはじめたのもこの頃からです。

――2016年のリオオリンピックの日本代表に決まった時は、どう思われましたか。
決まった時はあまり実感がなかったですね。どちらかと言うと、その時点でも五輪で結果を残すためにどうするかという方に意識が向いていたので、周囲に「五輪決まったね、おめでとう」と声をかけられても、「いやいや、まだこれからだし」という気持ちでした。自分の目標の通過点だったので、そこがゴールという気持ちじゃ無かったんです。
――跳躍種目は、日本と世界とのレベルの差が大きな競技でもありますよね。
頭ではもちろん理解していたのですが、現場で体感して、ある意味自信をなくしました。一生懸命やって五輪に出て、コテンパンにされて帰ってきて。五輪に出たことを、ポジティブにとらえられないほどのレベルの高さを目の当たりにして、世界にはとんでもない人たちがいるんだなと改めて思いました。全力を出す準備はできていたので本番でも緊張はしなかったのですが、全力でやり切れてこの結果かという思いが正直強かったです。あっという間に負けて実力不足を痛感しました。
きっかけをつくり、誰かの頑張りを後押しできる人間でありたい

――長谷川さんは「アスリートこそ社会に価値を還元しなければいけない」と話されていますよね。そう思うようになったきっかけを教えてください。
実業団に入って、「会社に選手を応援してほしい」という気持ちを持ったことです。でも冷静に考えて、他の従業員の方も大変な思いをして働いているので、陸上をやっている人たちだけを特別扱いして環境整備する理由なんてないんですよね。自分のその考えはおこがましいなと思い直しました。思えば、陸上競技自体では社会の役に立てることって無いんです。学生までは記録に挑戦したりスポーツで勝ったりするということは手放しに称賛されますが、三歩で遠くに跳べて人の役に立つかといえば別に立たないんです。興行として成立しているスポーツがあるなかで、僕の三段跳を観たいと思ってくれる人は地元でもほとんどいません。本質的に企業がお金を出すメリットがないと思ったからこそ、アスリートが社会に対してどんな価値を還元するかについて強く考えるようになりました。
――最初はどのような活動をしたのでしょうか。
何か貢献したい気持ちはあったのですが、何をすれば喜ばれるかまではわかっていませんでした。だからまずは自分から、「何か人の役に立ちたい」と思っていることを会社に相談しました。その結果、趣味で走るのが好きな人たちに走り方を教える活動をすることになったんです。その後、社内報でストレッチの仕方を教えたりもしました。そうした諸々の活動を行ううちに社内でコミュニケーションできる人も増え、自分自身も競技をやりやすくなりました。それに比例して応援してくださる人も増えていきましたし、僕自身も競技者として結果を残すというところではない目線を持てるようになりました。
――会社の外での活動、社会への価値の還元を強く意識したのは、伊藤超短波に入ってからですか。
アスリート的価値の還元を実現できたのは伊藤超短波に入社してからです。入社に際しても、そうした意思を伝えて応援していただきました。アスリートの社会での立場を確立させていくというのがこれからの時代はすごく大事だと思っています。日立のときに考えとして育っていたものが、伊藤超短波で形にでき始めた感じです。
――現在の社会貢献活動について教えてください。
いちばん行っている活動は、学校訪問です。1ヶ月に3、4校へ伺って、講演を行ったり指導したりしています。やはり運動が苦手だったという自身の経歴については驚かれることが多いですね。講演では「好きなことに思いきり挑戦することを前向きに考えられるようになれた」、「苦手だけど好きだから続けたいと思った」といった感想をもらうことが多く、話して良かったという気持ちになります。他にも「スポーツ×〇〇」という形で、スポーツでさまざまな社会貢献を考え、主に自分の地元を中心に活動をしています。たとえば市民活動センターの方とコミュニケーションをとると、「ゴミ拾いをやっているけど、活動を行っている人の中には普段運動不足の人が多い」という話を聞いたので、ゴミ拾いを始める前に体操の時間をとって指導する、というようなこともやっています。また、自分の地域にどういった運動施設があるかわからない人もいるので、運動施設の認知拡大のためにイベントを提案したりするようなことも行っています。僕自身が夢を持ったのがかなり遅かったので、もっと地元ではこういう施設がある、こういう人がいる、こういう機会がある、といったことを伝えていきたいと思ってます。スポーツを通じて自分の世界の広がりを感じられる体験があれば、それはスポーツ以外でも自分の可能性を広げようという気持ちになっていくと思いますから。僕自身が人生を切り拓いてもらってきたからこそ、そう強く思っています。

――長谷川さんの今の目標を教えてください。
まずは「アスリートでいること」にこだわっています。競技者として最後の可能性を突き詰めていくことを目指しています。自分も33歳になり、アスリートとして戦える時間も限られてきています。2024年のパリ五輪、2025年の東京で行われる世界陸上、これらに出場して記録を残すため日々努力しています。加えて、挑戦できる社会をつくっていきたいというビジョンを持っているので、スポーツコンシェルジュという形で困っている人や地域の課題をスポーツを通じて解決できる人になりたいと思っています。
――最後に、長谷川さんにとって「応援」とは?
応援というと、する側・される側を意識すると思うのですが、僕自身は一方通行ではなく、一緒に頑張るというイメージでとらえることが多いです。今までの自分の結果も、僕ひとりで成し得たわけではなく、支えてくれる人たちがいて初めて達成できたことでした。そもそも陸上を続けてこれたのは誰かの誘いや声掛けがあったからこそ。結果を待ってくれる人がいて、結果を期待してくれる人がいて、より一層頑張ることができる。それと同じように、きっかけをつくり、誰かの頑張りを後押しできる人間でありたいと思っています。